法令準拠から自主管理へ
令和3年7月19日に『職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会』の報告書が公表されました。これを受けて自主管理型に大きく変わろうとしています。
従来は、限られた特定の物質や作業に対する規制を遵守する「法令準拠」型でした。
これからは事業者自らが化学物質の危険有害性を調べる必要があります。その上で、従業員がケガや病気にならないような対策も自ら選択することになります。これが「自主管理」型への転換です。
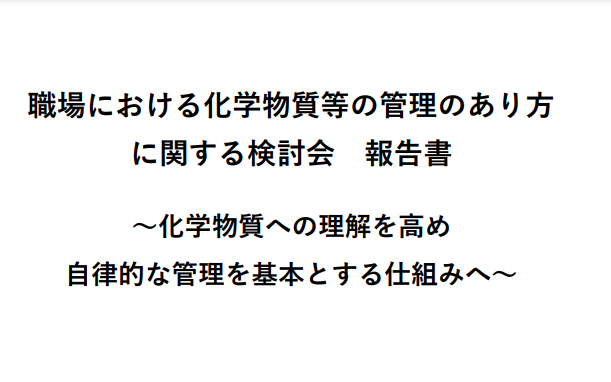
化学物質規制の方向性転換の背景には、労働災害と規制とのいたちごっこがあるようです。
- これまで使っていた物質が特化則や有機則などで措置義務対象に追加される
- 措置義務を忌避して危険性・有害性の確認・評価を十分にせずに規制対象外の物質に変更
- 対策不十分により労働災害が発生
- 労働災害が発生すると当該化学物質が規制される
また、化学物質による休業4日以上の労働災害の約8割は、具体的な措置義務がかからない物質により発生しているとのことから、現在の規制では労働災害の発生を防げていません。
そこで、特定の化学物質に対する個別具体的な規制から、危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求めることになります。そして、達成のための手段は指定しない(事業者の自律的な管理に委ねる)方式に大きく転換するのです。
新たな仕組み
新たな自主管理の仕組みのポイントは以下の通りです。
- 国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質に、以下の事項を義務づけ
- 危険性・有害性の情報の伝達
- リスクアセスメントの実施
- 労働者が吸入する濃度を国が定める管理基準以下に管理
- 保護眼鏡、保護手袋等の使用
- 労働災害が多発し、自律的な管理が困難な物質や特定の作業の禁止・許可制を導入
- 特化則、有機則で規制されている物質(123物質)の管理は、5年後を目途に自律的な管理に移行できる環境を整えた上で、個別具体的な規制(特化則、有機則等)は廃止することを想定
国によるGHS分類は、今後数年をかけて約2,900物質まで増える予定です。措置義務対象の化学物質が大幅に増ます。一方で、管理基準を達成する手段は、事業者がリスクアセスメントにより自ら選択することになります。
これらの変更を規定する、改正労働安全衛生規則等が令和4年5月31日に公布されました。そして、令和5年4月1日、令和6年4月1日に順次施行されます。
まとめ
新たに追加される措置義務対象化学物質を製造あるいは使用している事業者の方、溶剤や薬剤を使用している社員の健康を守りたいと考えている経営者の方、今回の法改正を機に自社の化学物質管理体制を構築/見直し、新たな化学物質規制の変化に対応しませんか?